
対人援助職にとって「自己覚知」はとても大切といわれるけど、この自己覚知についてわかりやすい説明はないのかなぁ。
ここでは、こんな疑問に答えたいと思います。
本記事の内容
- 自己覚知の前に必要なこと
- 自己覚知の必要性について
- 自己覚知の難しさ
- 自己覚知を行っていくために
記事の信頼性

医療・高齢・地域福祉でソーシャルワーカーとして、対人援助職20年以上。現職は、地域福祉機関で管理者をしています。
社会福祉士養成校等で、社会福祉士等の養成に関わって約10年。
有資格は、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員、公認心理師。ブログ月間1万PV。
対人援助職として専門性を身につけていく上では、この「自己覚知」がどうしても必要といわれます。ここでは、ソーシャルワーカーとしての筆者の経験を踏まえ、対人援助職(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士・介護支援専門員・保健師・看護師等)にとって、その理由についてわかりやすく触れて、自己覚知について解説していきたいと思います。
自己覚知を理解するために

自己覚知の前に
自分自身を見つめなおすということは普段なら行わないですよね。
私の学生時代であれば、周りから叱られた時に「そんなにダメだったかな」と、そこそこ?反省?するぐらいです。
たとえば、ソーシャルワーカーとしての養成は、大学入学後20歳前後から始まります。他の専門職も同じ時期でしょう。
社会的にも自立してくると、個人としての価値観はもちろんのこと、人格もしっかり形成されています。
ただ、世の中に自分を客観視して見つめなおす機会がたくさん用意されているわけでありません。
自己覚知の必要性について
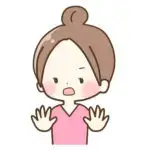
「先生、私は自己覚知とかしている暇はないんです」
何年か前、学生(中年期の方)にこのように言われたことがありました。
この自己覚知に強い抵抗を感じたりしたら、臨床に入ってからとってもしんどいです。
現に、その学生は実習中、自己理解について強い指摘を実習指導者から受けて、とても辛そうな様子でした。
きちんと自己覚知できなければ、私は現場で、何人もの対人援助者が適切な援助関係が構築できず、バーンアウトしていくのを見てきました。
バーンアウトとは燃え尽き症候群と言って、簡単に言うと仕事などに突然やる気を失ってしまうことをいいます。
私の場合、関わっている社会福祉士の養成課程で学生に話すのですが、せっかく福祉に関わる職種を選んでくれたわけですし、「バーンアウトしないように、福祉の仕事は続けてほしい。」と強く思います。
自己覚知ができなければ、クライエントとの適切な援助関係を構築することができません。そして、援助者自身を守るためにも、自己覚知が必要になります。
自己覚知への手がかりⅠ(バイスティック氏より)
バイスティックは、自己覚知について次のように述べています。
受け止める上で障害になるもの 障害となるものの源泉は、ほとんどつねに一つである。それは、いくつかの領域におけるケースワーカーの自己理解の欠如である。この欠如がクライエントのもっている現実認識を見誤らせ、クライエントをありのままの姿で捉えることを妨げる。
引用:ケースワークの原則 援助関係を形成する技法 誠信書房 F.P.バイステック
このケースワークの原則の書籍の中には、たくさんの自己理解(自己覚知)についての記載が具体的に記されています。
ケースワークの7原則の内、特に「受容」の原則においては、たくさんの自己理解の説明がなされています。
もう一つ言葉を挙げましょう。
自己理解が、自分自身による自己の受容を進め、究極的にはケースワーカーの他者を受け止める態度や行為を高めていく。
と説明しています。
私たち対人援助職は、人が問題に直面して、援助を求めているクライエントのいろいろな状況を理解しなければなりません。
「他者をどれだけ理解することができるか」ということが援助職には突きつけられているわけです。
その対人援助者にとって必要な「他者理解」は「自己理解」によって高められていく。と説明しているのです。
自己理解と他者理解なんて、別物と思いがちですが、そうではなくて、とても密接であるということを私たちは知らなくてはいけません。
他にも自己覚知についての記載がたくさんされていますので、自己覚知をより学びたい方にとっては、必読と言えます。
自己覚知への手がかりⅡ(渡部律子氏より)
もう一つ自己覚知を理解するうえで、良い引用があるので参考にしましょう。
自己覚知
自分自身をより客観的に見つめることができる力です。
効果的な援助のためには、援助者が自分自身の感情や態度を認識しておくことが重要です。
自分はどんな考え方をしがちか。どのようなタイプのクライエントには共感しやすく、逆にどのようなタイプのクライエントには苛立ちを覚えがちなのか。
多くの援助者の持つ特徴が援助関係の形成に関係してきます。
このような自分自身の特徴を冷静に振り返り、援助の障害になっている自分の考え方や行動が理解でき必要に応じて軌道修正していくことが大切です。
この「自己覚知」ができる力というものは援助者にとって「必要不可欠」なものです。
引用:渡辺律子 相談面接理論と実際
ここで、引用したこの書籍は、現場でおざなりになりやすい自己覚知を含め、筆者の体験に基づいて「わかりやすい言葉」で丁寧に解説されている良書になります。
分かりやすく自己覚知を、学びたい方には大変お勧めになります。
自己覚知の難しさについて
これほどまでに必要なのに、なぜ難しいのか・・・。
それは自己覚知は自分の態度や傾向を知ることですが、時として、自分自身の嫌なところ、ネガティブなところもふくめて見つめなおすことになるからです。
自分自身のネガティブなところは、わかっているけどそんな毎日振り返る機会があることではありません。
これを意識して、振り返る作業になるので、ずばり気分の良くない要素を含んでいます。
例えば、ソーシャルワークの原理は、社会正義、人権、集団的責任、および多様性尊重です。自分で言ってしまいますが、本当に素晴らしいものです。
ソーシャルワークについては以下を参考にしてくださいね。
ソーシャルワークを体現できれば、権利を擁護するスーパーマンでしょう。
だからこそ、以下の点に注意しなければなりません。
- 理想の対人援助職と生身の自分がたちまちいっしょになりません。
- 変身ベルトは存在しないのです。そこは当然、不一致になります。
- 自己覚知は、その作業途中で自己否定に陥りやすい。
自己否定の具体例について(筆者の体験Ⅰ)
理想の対人援助職と生身の自分が一緒にならない、不一致とはどういったことでしょうか?
具体的な例、筆者のソーシャルワーカーとしての体験を挙げてみていきましょう。
例えば、私めざしは強面の方がちょっと苦手です。
なので、クライエント本人がそういう強面だったら、「ちょっとこわいなぁ」と思ってしまいます。
でも、ソーシャルワーカーとして、問題に直面しているクライエントのことをしっかり受け止めないといけないのに、自分の苦手意識によって「ちょっとこわい」と思ってしまって、受け止めきれていないのではないか?
ソーシャルワーカーである自分が、クライエントのことをそんな風に思ってはダメだと私は思ってしまいました。
自己否定の具体例について(筆者の体験Ⅱ)
もう一つ例を挙げましょう。
私は、親族の関係で、ある方言(九州地方)に感情移入が強くなる傾向があります。
病院のソーシャルワーカーとして勤務している脊損のクライエントがその地方出身の方でした。親近感が湧くことで、支援したいという感情が強くなり、よくベッドサイドへ行くようになりました。
クライエントは住居不定でしたので、新たな住居設定を行う必要があり、独居での在宅支援は相当の準備、支援を行う必要がありました。
でも、他にも担当の患者さんがいるのにも関わらず、私の個人的な好意のある感情によって、その人だけに支援が注力されている可能性は否定できなかったと思います。
ソーシャルワーカーである自分が、全体のバランスを欠いた支援を行っているのではないか?と私は思ってしまいました。
不一致が自己否定になる

自分はソーシャルワーカーなんだから、そんな風にクライエントのことは思ってはダメだ。
クライエントに適切な支援ができないんじゃないの?
実習や現場に入れば、このような事を思ったことないでしょうか?
生身の自分が持つ、クライエントに対する負の感情は、ソーシャルワークの価値とは相反するものだと思ってしまうのです。
また、正の感情についても、援助という観点から見れば、適切なのかどうかわからなくなる時があります。
クライエントの理解において、特に受容する過程において、援助者のさまざまな反応の中に、クライエントに好感を持つなど正の感情があったり、また逆に否定や、嫌悪感があったり、負の感情があります。
ソーシャルワークを実践するソーシャルワーカー像というものが必ずあるでしょう。
その理想像があるのにも関わらず、生身の自分はクライエントを受容できていない。また、感情移入しすぎている自分がいることで、理想と生身が、ずれればずれるほど、自分はダメだと思ってしまいがちです。
素晴らしいソーシャルワークを実践するはずの自分(ソーシャルワーカー)が、クライエントをしっかり支援できないダメな存在。
この不一致が自己否定を引き起こすのだと筆者は考えます。
自己覚知を行っていくために必要なこと
援助者のどんな感情も大切にする
では、自己覚知を行っていくためにどうしていくのが良いのでしょうか?
たとえば、先ほどの筆者の例で、強面のクライエントに「怖いな。いやだな」と思ってしまった自分の否定的な感情を否定しないことです。
「怖いな」と思っていいということです。
そして、私は、「そんな風に思ったの自分の反応は、これまで培ってきた大切な人生なんだ。」
という、とらえ方をしています。
クライエントと同様にソーシャルワーカーの人生も大切なのです。あなた自身の価値観や傾向を、まず大切にすることです。
軌道修正すること
そして、そこから「軌道修正」(渡邊律子)することがとても大切になります。
自分を客観視できるようになって、すこしずつ軌道修正できればいいんです。
負の感情とともに、正の感情についても、大切なのは、同じようにその客観性です。
軌道修正とは、「怖いな」と思わないようにするということではありません。また、親近感が湧かないようにすることでもないのです。
「怖いな」とまず援助者が自覚すること。そしてそこから、どのようにクライエントにアプローチしていくのか。その適切なアプローチを考えて支援すること。
「ちょっと怖いな」でも、ちゃんと話を聞こうとか。自分の傾向をきちんと客観視することです。ここが大切になる軌道修正です。
クライエントに入りすぎず、距離を取りすぎないようにするために、自身の傾向や価値観を理解する自己覚知が必要になります。
また、自分の価値観もまた年月を通して、変わっていきますので、学生時代や新任で終わることなく、勇気をもって続けることが大切だと思っています。





